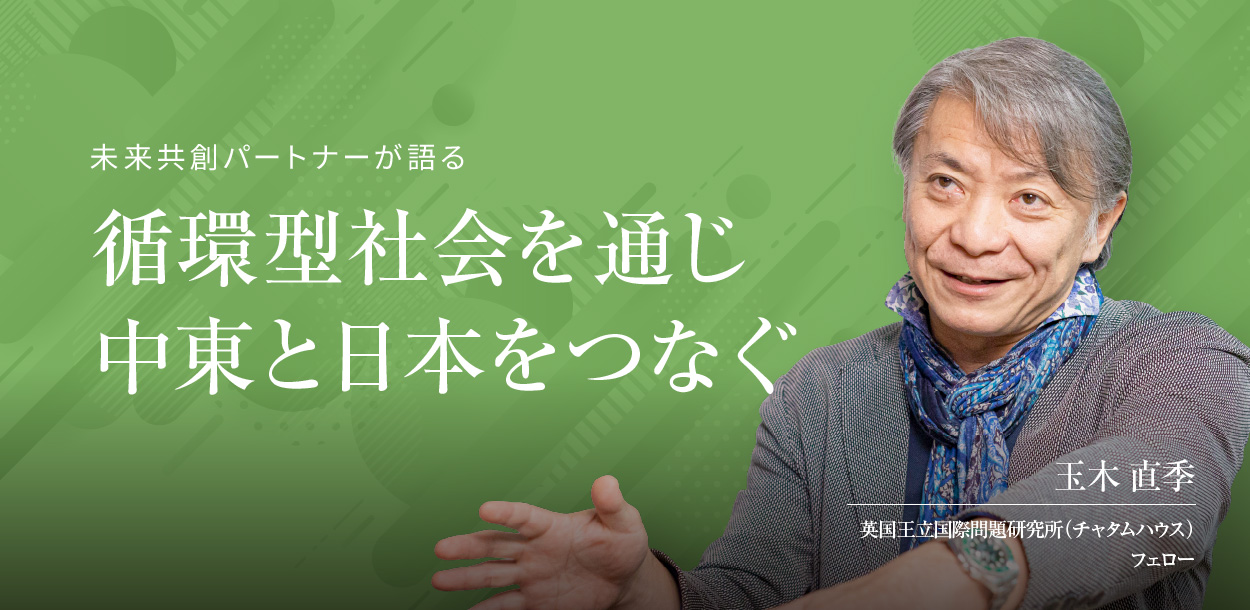
YOKOGAWAの「未来共創イニシアチブ」は、共創的な対話を通じ、国や産業の枠を超え、超長期の視点で未来シナリオを描く。本活動における視座・視野をより高く広いものにするため、未来共創パートナーとして招聘したのが、英国王立国際問題研究所(以下、チャタムハウス)のフェローを務める玉木直季[以下、玉木(直)と記載]氏だ。
玉木(直)氏は、プロジェクトファイナンスや地政学という見地から、循環型社会(サーキュラーエコノミー)を主要な研究テーマに据え、サウジアラビアを拠点に世界で活躍している。
今回のインタビューでは、なぜ中東に注視するのか、また循環型社会で日本が貢献できることを中心に、地球の未来を考える上で欠かせない新たな見解を語ってもらった。
※本記事では、所属する組織ではなく、個人の見解として語っていただきました
※所属や役職は記事制作時(2025年11月)のものです
※取材場所は、MIRAI LAB PALETTE(MLP)
YOKOGAWAと中東との長い関係
原油を中東諸国に大きく依存する日本。一方で、サウジアラビアは石油に依存しない未来の経済を見据え、2025年2月に総額149億ドル(約2兆円)の大規模AI投資計画を発表し、世界を驚かせた。日本とはいまだに地理・文化的な隔たりが大きいが、さらなる経済発展が見込まれる中東への理解と関係構築が、今後の重要な鍵となるといわれる。
YOKOGAWAは、1981年に中東に本格進出。これまで中東地域で多くの実績を築き、事業を拡大してきた。中東・アフリカでの総売上は全体の17%以上を占め、YOKOGAWAの最重要地域の一つとなっている(FY2024年実績)。

Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c) |Bahrain Office
玉木(直)氏とYOKOGAWAとの接点は古く、彼が20代だった東京銀行(現三菱UFJ銀行)バーレーン支店赴任時代にさかのぼる。同氏は、YOKOGAWAの中東・アフリカ地域の統括子会社である「Yokogawa Middle East & Africa B.S.C. (c) (YMA)」を顧客として担当していたからだ。

多様な価値観を求め、日本からカイロへ
玉木(直)氏が中東へ向かった経緯は、非常にユニークだ。
中学から東京の一貫校でエスカレーター式の教育を受け、その固定的な価値観に対し、どことなく居心地の悪さを感じていたという。大学卒業後、東京銀行に入行すると、地方支店への赴任を自ら志願した。
「自分が感じる閉塞感や違和感から抜け出したかったんです。銀行内に、アラビア語を含む語学研修制度があることを知ったとき、即座に留学を決めました。行き先は、学生時代に訪れたエジプトのカイロ。『いやこれだ!』と思ったんですよね」

イスラム社会のカイロで、玉木(直)氏は多くのカルチャーショックを受け、戸惑った。タクシーや買い物での交渉など、人やモノ、時間次第でルールや値段が変わることから、「人の数だけ価値観がある」と学んだ。そして、日本での固定観念から解放され、中東での暮らしで出会う不思議な感覚に、次第に魅了されていったという。
GDP(国内総生産)だけを見てよいのか?
カイロ留学後、玉木(直)氏は中東とのつながりを深めていった。長年にわたる中東でのファイナンス業務を経験し、ようやく気付いたのが「循環型社会」の大切さだった。
「銀行では、中東向け大型案件に資金を提供するプロジェクトファイナンスをやってきました。YOKOGAWAさんも関わっておられる石油化学、オイルリファイナリー(石油精製)、発電所など、大型のプロジェクトにも融資をしてきました。

Yokogawa Middle East and Africa Regional Office L.L.C.|Saudi Arabia Office
石油や天然ガスといったエネルギー産出国の中東で実現されるプロジェクトは、基本的に炭化水素ありきなんです。つまり僕は、地球温暖化に加担してきたんですね」

同氏は、さらに自問した。
「プロジェクトファイナンスの目的は、国の経済や産業の開発ですが、『果たして僕は何を開発したんだろう?』と疑問に感じました。いわゆる国の経済=GDPを増やすことには、貢献したかもしれない。でもそれは、果たして人々の幸せにつながったのだろうかと。
僕がファイナンスしたプロジェクトによって、地球温暖化を促進する炭酸ガスをいっぱい出した訳ですよね。地球からしたら、『何してくれちゃってんのよ』という話なんです」 こうして玉木(直)氏は、自身の追求テーマを循環型社会に絞り、研究や投資・アドバイザリーの分野へと移行していった。
サウジアラビアを中心に、地球の課題解決に挑む
「今、地球が抱えている最大の課題は、人口爆発と経済発展によるものです。2050年までに人口増加が予想される17億人のほとんどは、アフリカ・中東・南アジア・東南アジアの広域にわたる環インド洋地域に集中しています。その食料とエネルギー、そして製品を、どう供給するのか? これまでと同じやり方では、インド洋は廃プラスチックでいっぱいになり、アフリカ大陸はごみで埋まる。地球は破綻してしまいます」
それらの課題解決に向けて、日本には何ができるのだろうか? 玉木(直)氏は、同地域の多くはイスラム教国家であることから、そのリーダー格たるサウジアラビアが鍵になると言う。

「サウジアラビアは、メッカとメディナというイスラム教の二大聖地を抱え、人口も約3,500万人と多い。またオイルマネーのおかげで、リーダーとして振る舞えるだけのお金も持っています。さらに、イスラム圏でのいわば世界銀行的な役割を果たす『イスラム開発銀行』もあります。今まさに、サウジアラビアは国を開放して大きく変化を遂げるための、さまざまな施策を行っているのです」
しかし、サウジアラビアのごみのリサイクル率はわずか5%であり、95%は砂漠に廃棄しているのが現状だ。同国は、2035年までにリサイクル率を90%にする目標を掲げており、そこで日本が貢献できるはずだと、玉木(直)氏は見解を示す。
「循環型社会に向けた日本の高い技術とフィロソフィーで、サウジアラビアの課題を解決する。成功したら、その手法を環インド洋地域にも広められます。『インテルインサイド』という言葉があるように、このサウジモデルは『ジャパンインサイド』なんです。イスラム世界を中心とするグローバルサウスへのゲートウェイが、サウジアラビアだという訳ですね」
日本のフィロソフィーを世界に
資源が乏しく、自然やものに敬意を払う文化が根付いてきた日本では、「もったいない」精神が育まれてきた。また、平地が少なくごみを捨てる場所が限られた地理的条件も、循環型社会を実現するリサイクル技術の高度化を後押しした。
「国連などでは、『環境問題は技術とお金で解決できる』という見解が多く見られます。でも台風や地震などの自然災害が多い国土に住む日本人にとって、自然は恵みであるが、『征服できない脅威』でもある。まさに、『森羅万象の中に我あり』という感覚なんですね。
これこそが日本人のフィロソフィーであり、環境問題解決のヒントになる。それを伝えることが、循環型社会に向けた日本の役割だと思うのです」

詳細
未来共創イニシアチブメニュー

HOME
YOKOGAWAが推進する「未来共創イニシアチブ」のトップページ

インタビュー
「未来共創イニシアチブ」に関わる社内外の関係者が、対話を通じ、多様な視点で語る活動の価値や意義

活動概要
シナリオプランニングを活用した次世代リーダー育成と、境界を超えた共創ネットワーク構築を目的とした活動の紹介

活動への想い
「正解のない時代」に生まれた、活動発足の背景や志

未来シナリオ
未来を担う若手社員たちが、シナリオプランニングと共創的な対話で描いた「未来シナリオ」

シナリオアンバサダー
YOKOGAWAの各部門から選ばれたミレニアル世代中心のシナリオアンバサダー紹介と成長や学び

未来共創ネットワーク
YOKOGAWAグループ内外のサポーターやパートナー、個社と緩く繋がり、産官学連携で築くネットワーク

Sponsor Article
米国発テックカルチャー・メディア『WIRED』に掲載された、「未来共創イニシアチブ」の英文記事
本件に関する詳細などは下記よりお問い合わせください
お問い合わせ